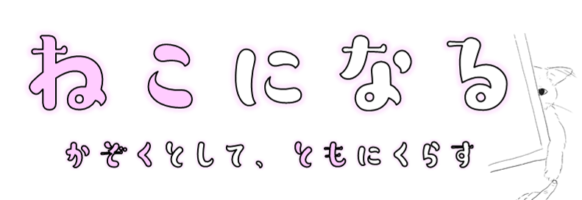お気に入りの家具で爪とぎをする愛猫の姿を見つけて「やめて!」と叫んだ経験のある人も多いのではないでしょうか?
できることならやめさせたいと思いますよね。
ですが、残念ながら爪とぎは猫の習性なので完全にやめさせることはできません。
しかし、家具で爪とぎをしないようにしつけることはできます。
今回は、猫が爪とぎをする理由とすぐに実践できる爪とぎのしつけ方をご紹介します。
目次
猫が爪とぎをする理由とは

猫は、なぜ爪とぎをするのでしょうか?
「爪のケアをするため!」それも正解です。
しかし、それだけではありません。
猫は実にさまざまな理由で爪とぎをするのです。
爪のケア
狩猟動物の猫にとって爪は狩の武器であると同時に自分の身を守るための大事な武器でもあります。
その爪をいつでも使えるようにケアをするのが爪とぎです。
猫の爪は、玉ねぎのような層になっています。
爪とぎをすることで外側の古い爪がはがれ落ち、常に鋭い爪を保つことができるのです。
マーキング
猫の肉球には匂いを出す臭腺(アポクリン腺)があります。
爪とぎをすることで、匂いをこすりつけて、縄張りの主張をしていると考えられています。
つまり、マーキングをしているのです。
猫の世界では、強い猫ほど高い位置に匂いをつけるとされています。
そのため、思いっきり伸びて爪とぎをする猫もいます。
つい、応援したくなりますよね。
ストレス発散
猫はジャンプに失敗したり、嫌なことがあったときに爪とぎをすることがあります。
これは、ストレスを発散したり、気分を落ち着かせたりするための爪とぎで、「転移行動」と呼ばれています。
リラックスやストレッチ
猫は遊んで興奮しすぎたときや寝起きに体を伸ばすために爪とぎをすることがあります。
これは気持ちを落ち着かせ、リラックスをするための爪とぎです。
かまってほしい
飼い主さんの前で爪とぎをはじめたら、それは自分に注目してほしいという主張です。
前に爪とぎをしていたら注目してもらった、という経験からそのような行動をするという説があります。
なんだかかわいいですね。
爪とぎ器にはいろんな種類がある

爪とぎ器には段ボールや麻などさまざまな素材の商品があります。
それぞれ耐久性や値段に違いがあり最初は悩んでしまうかもしれませんね。
最終的には愛猫の好みで!とはなるのですが、それぞれの特徴を把握しておきましょう。
段ボール製

猫の爪とぎ器の定番といえば段ボール製。
ホームセンターやドラッグストアのペットコーナーでもだいたい売っていますよね。
段ボール製の爪とぎを好む猫も多く、安価なため愛用している飼い主さんも多いのではないでしょうか。
形状も板状のシンプルなものから、ベッド型、ソファー型、ハウス型などさまざまな形のものがあり、インテリアとしても優れています。
ただし、爪とぎをするとカスが出やすく、耐久性が低いため定期的に買い替える必要があります。
最近はカスが出にくい強化段ボール製の爪とぎ器もあるので、気になる方はそちらがおすすめです。
麻・綿などの紐

麻や綿の紐をポールに巻き付けているのが一般的ですが、最近はかわいらしいサボテンやきのこの形をした商品が人気で、SNSでもよく見かけますね。
キャットタワーの柱についている爪とぎの多くが麻製のものです。
段ボール製と比べると耐久性がありカスが出にくいのがメリット。
ホームセンターやドラッグストアでも購入できるのでおすすめです。
布製
布製の爪とぎ器は、土台に絨毯を貼り付けたものや、カーペット型のものがあります。
カスが出にくく耐久性も抜群ですが、販売数が少ないのが難点です。
カーペット状のものはソファーに掛けて置いたり、家具や壁に貼り付けたりして使用することができます。
爪とぎをしてほしくない場所のガードにもピッタリです。
木製

外で暮らす猫は木で爪とぎをします。つまり、木製の爪とぎは猫にとって自然に近い爪とぎ器なのです。
家具や柱で爪をとぐ猫は、ほかの爪とぎ器よりも木製のほうを好むのでは?という意見もあります。
家具で爪とぎをされてお困りの方は検討してみてはいかがでしょうか。
ただし、木製の爪とぎは耐久性には大変すぐれていますが、高価なのが悩ましいところです。
爪とぎのしつけ方

しつけと言われるとなんとなく身構えてしまう飼い主さんもいると思いますが、やり方は簡単なので、ぜひ実践してみてくださいね。
子猫は、親猫やほかの猫たちの行動を真似て学習します。
爪とぎを教えるときは、飼い主さんが爪をとぐ動作をして子猫に見せると、あっさりと真似をしてくれることがあります。
真似をしてくれないときは、猫の前脚を持って、爪とぎ器をバリバリと引っ掻くようにしてみてください。
このときに、肉球をこすりつけるようにすると匂いがつくので、使ってくれることもあるようです。
大人の猫ならマタタビで誘導するのもありです。
爪とぎ器に付属していることも多いので、ぜひ活用しましょう。
どちらにしても、しつけのコツは「ほめること」です。
爪とぎ器を上手に使ったら、高めの落ち着いた声でほめてあげましょう。
ほめるときに、撫でてあげるとベストですね。
爪とぎのしつけのコツと対策

爪とぎのしつけを実践してみたけど上手くいかないな、とお悩みの飼い主さんも多いと思います。
そんなときは、以下を参考に対策をしてみてください。
猫を叱ってはいけない
猫がやってはいけない場所で爪とぎをしているのを見つけるとつい「ダメ」と言いたくなりますよね。
でも、ここはぐっと堪えましょう。
叱っても猫は理解できません。
それどころか叱り方次第では猫との信頼関係にひびがはいってしまうことも。
してはいけない場所で爪とぎをしていたら、そっと爪とぎ器をあてるか、爪とぎの場所まで誘導してあげましょう。
お気に入りの爪とぎ器を見つけてあげよう
猫の爪とぎのしつけを成功させる鍵は「お気に入りの爪とぎ器を見つけること」だと思っています。
それくらい猫は好みにうるさい動物なのです。
爪とぎ器にはさまざまな素材と形状のものがあります。
最初は痛い出費になりますが、複数の素材と形状のものを用意して愛猫のお気に入りを見つけましょう。
爪とぎ防止対策グッズを活用しよう
猫に家具や壁で爪とぎをされたらたまりませんよね。
そんなときは、市販の爪とぎ防止の保護シートを使うのがおすすめです。
猫はつるつるした場所では爪とぎをしないので、ビニールシートなどつるつるしたものを貼り付けるだけでも効果があると言われています。
側には爪とぎ器を置くようにします。
爪とぎ器を使ったらほめてください。
それでもやめてくれない場合は、逆の発想で爪をといでもよい場所にしてしまいましょう。
貼り付けるタイプの爪とぎ器やソファーなどにかけて使えるカーペット型の爪とぎ器がおすすめです。
ほかにも、猫が嫌う匂いや味がする忌避剤を塗る方法もあります。
爪をこまめに切ることで被害を小さくする
愛猫の爪をこまめに切ることで家具や壁のダメージを減らすことができます。
子猫は10日ほど、1歳ごろからは2〜3週間ほどで元通りになりますので、そのくらいのペースで切ってあげましょう。
爪には血管が通っているので深爪にならないよう先っぽを「ちょい切り」が基本です。
まとめ
爪とぎのしつけのコツは猫のお気に入りの爪とぎを見つけること。
そして、覚えるまで繰り返し教えることです。どうしても上手にいかないときは、忌避剤などの対策グッズに頼るのもおすすめですよ。
お互いストレスにならない範囲で頑張りましょう。